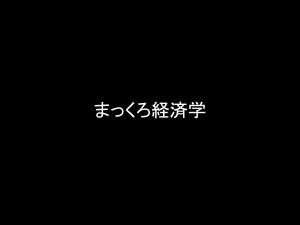35. ボランティア求む!
昨年のことになりますが、小田原の市場で相模湾の定置網でとれた「ケンサキイカ」を買いました。でも実は、それが本当にケンサキイカ(Uroteuthis edulis)かどうか調べてみたかったのです。18個体のDNA(遺伝子)を調べてみたところ、なんとそのうち4個体がアジアケンサキイカ(Uroteuthis duvaucelii)という別の種類でした。このイカは、南シナ海やフィリピンのあたりにたくさんいる種類で、ふつうは日本の海では見つかりません。おそらくフィリピン海あたりから黒潮に乗って、相模湾まで運ばれてきたと想像されます。実際、フィリピン海にはこのアジアケンサキイカがたくさんいます。
この話を釣り好きの方にしたところ、関東の太平洋側で大きな「ケンサキイカ」を釣った人がいると教えてくれました。その人がイカの吸盤についているリングを観察して、私のブログに載せていた写真と見比べたところ、ヒラケンサキイカ(Uroteuthis chinensis)っぽいというのです。この種類もフィリピン海に多く住んでいる南方系のイカで、やっぱり黒潮で運ばれてきた可能性があります。確定するにはDNAの検査が必要ですが、こういうことがあるととてもワクワクしますね!
最近では、温暖化の影響で、熱帯の魚やサンゴが伊豆の海でも見られるようになっています。ですから、南のイカが黒潮に乗って日本まで来ること自体は、もはや不思議ではなく、自然なことと言えます。ただし大事なのは、そのイカたちが日本の海で冬を越して、子ども(卵)を産むことができるかどうかです。今のところ、ケンサキイカなどの仲間が日本周辺で大きな産卵場を作っている例は見つかっていません。つまり、日本の海はまだ、Uroteuthis属にとっては少し冷たいのかもしれませんね。でも、そのおかげで、成長がゆっくりになって、刺身にちょうどいい大きさのケンサキイカが獲れるという面もあるのです。
イカの仲間は、今から1億年くらい前の中生代後期、テチス海という赤道付近の浅くて温かい海でたくさん進化しました。その後、大陸が動いてテチス海がなくなっていく中で、イカたちはだんだん北や南の海へも広がっていったと考えられています。ケンサキイカやアオリイカなど、今でも温かくて浅い海を好む種類が多いのは、そのときの性質を今も引き継いでいるからかもしれませんね。
もし太平洋沿岸でイカ釣りをしていて、「なんかこのケンサキイカ、いつもとちょっと違うぞ?」と思うイカが釣れたら、ルーペなどで吸盤のリングを見てみてください。そして、私のブログの写真と比べて「これは違う種類かも」と思ったら、ぜひ連絡してください。できればそのイカを丸ごと冷凍保存してもらえるととても助かります。大きすぎる場合は、胴の長さ(外套背長)を測って、性別が分かれば性別も。さらに成熟の情報があれば文句なしです。そして、体の一部(小指の先ほどの大きさ)を切って冷凍保存してください。DNAを調べます! それ以外の部分は、食べていただいてOK。味や食感も教えていただけると嬉しいです。たぶんケンサキイカと変わらないと思いますが…。
いまのところ、謝礼などは出せません(すみません…予算がないです)が、もし研究論文になったら、ご協力いただいた方のお名前を謝辞に載せさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします!