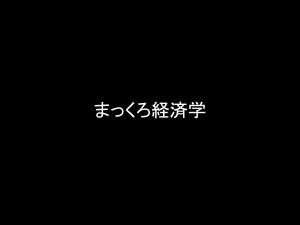21. 平衡石と経験水温、ふたたび
先日スルメイカに関するイカ男の論文が初めて出版されました。この論文の主な内容は、スルメイカの平衡石を構成する炭酸カルシウムのカルシウムに対するストロンチウムの比率(Sr/Ca比)とそのイカが経験した水温の間にどのような関係があるかを検証したものです。イカの研究についていくらかご存じの方は、そんなの当たり前ではないかと思われるかもしれませんが、実はそれほど当たり前でもないのです。
平衡石のSr/Ca比と経験水温については多種のイカで研究されてきました。実例の紹介は省きますが、負の相関があるという報告が多数である一方、関係がないとか、なかには正の相関があるといった報告もあります。また、経験水温とは負の相関があるものの、別の要因によっても変化するという報告もあります。イカ男が以前おこなったケンサキイカの平衡石では負の相関を支持する論文が大多数なのですが、スルメイカの平衡石では研究例が少ないため疑問視する声もあります。といった事情で、本格的にスルメイカの移動を研究するためにはまずSr/Ca比と経験水温の関係を検証しておかなければならなかったのです。
本来であれば、ケンサキイカの時と同じように、水温を管理した水槽でイカを飼育する方法が一番よいのですが、残念ながら現在のイカ男には自由に使える飼育施設がありません。そこで、まったく別の方法を選択しました。まず、北海道ではシーズンの初物となる7月に積丹半島近海で漁獲されたスルメイカを使いました。このイカが1月にふ化したことは平衡石にみえる輪紋の計数で分かっています。さらに、長年の研究からふ化場所は対馬海峡か東シナ海北部の大陸棚であることは既知でした。したがって、冬から春にかけて、対馬暖流によって北上したことが推測されます。おそらくこれらの個体は対馬暖流の第1分枝か第2分枝によって日本海を東北地方沿岸から積丹半島近海まで移動したはずです。一方、分析した平衡石のSr/Ca比は生活史の後半(4月から7月)において、ほぼ全て同じように減少していました。そこで、コンピュータ・シミュレーション(粒子追跡実験)をもちいて、漁獲日に漁獲場所から時間を遡るように4月まで粒子を移動させたところ、粒子は日本海のほぼ中央に位置する大和堆付近まで戻っていきました。この粒子が移動した海域の水温は4月から7月にかけて単調に上昇していたことから、スルメイカ平衡石でもSr/Ca比と経験水温の間には負の相関があることが確かめられ、さらにその換算式も得たのでした。
平衡石のSr/Ca比から経験水温を復元するという考えは、同じ炭酸カルシウムのアラゴナイト結晶構造をもつサンゴ骨格から古海水温を推定した研究に由来します。もちろん、炭酸カルシウムに含まれるストロンチウム濃度は溶液の温度と負の相関にあることは化学実験で確かめられている熱力学的な事実です。では、なぜイカの平衡石では疑問視されるのでしょう。それは、生体の平衡胞の中でおこる反応だからです。たしかに平衡胞内には無機的な物質だけでなく、酵素などの有機的な物質もあるはずです。なので、必ずしも室内実験や海中に露出したサンゴでおこる現象とは同じとは限らないということですね。ただし、熱力学の法則(化学反応は自由エネルギーが減少する方向に向かう)に逆らう方向へ反応をすすめるためには、外部から余分なエネルギーを加える必要があります。もし、ストロンチウム濃度の増加が平衡石に悪影響を与えるのであれば、特別な酵素が存在してストロンチウムの混入を排除している可能性があります。また、まったく別の化学反応の副反応として、結果的に逆向きの反応を進めている可能性もあります。いずれにしても、そのような酵素があるのかどうか調べてみなけれなりませんが...
ただ、イカ男がこれまでケンサキイカやヤリイカ、スルメイカ、ホタルイカの平衡石Sr/Ca比を分析した結果では、経験水温と負の相関があると仮定してほぼ矛盾がありませんし、まして無関係であるとは思えません。つまり、無関係と考えるにはあまりにも負の相関がありすぎるのです。なので、無関係と報告している論文を目にすると、たとえば飼育サンプルを用いた実験ならば、イカのコンディションはどうだったのか? 温度管理は万全だったのか? などと疑問をもってしまいます。イカ男がケンサキイカで妥当な結果がでた要因は、唐津の漁師さんが朝どれの個体をほとんどダメージなく飼育施設まで活魚車で搬送してくれたからだと信じています。彼らはおそらく世界でいちばんイカのハンドリングに卓越した人たちです。また、野生のサンプルを用いた場合はSr/Ca比の分析方法は正しかったのか? などと疑問をもってしまいます。ストロンチウムやカルシウムを分析する装置(EPMA)はいまでは汎用機に近いものですが、正確に分析をするためには専門技術者のサポートが必要です。
もちろん、平衡石のSr/Ca比には水温以外の影響もありえます。たとえば、海水中に含まれる微量元素濃度や餌生物の違いです。この点で、イカ男の研究はとても幸運だったのかもしれません。なぜなら、扱ったイカのほとんどは対馬暖流系のイカだったからです。対馬暖流系の生物とは、主に黒潮から派生して東シナ海を北上して日本海を北海道西部へと向かう暖流のなかで生まれて成長する個体群と考えてください。これらの個体群はいくらかの季節変化はあるとはいえ、同じ海水にさらされ、同じ生物種を食しているはずです。よって、いちばん変化しているのは周りの水温ということになるでしょう。さらに平衡胞があるイカの頭部は、魚類などとは違って頭骨がなく、まわりに熱を発する筋肉もなく、鱗もありません。海水温の変化を直接受けているはずです。したがって、その結果、Sr/Ca比には海水温の影響が顕著にあらわれるとイカ男は考えるのです。
さて、これで本格的にスルメイカの移動と再生産システムを学術的に発表する準備が整いました。今後ブログで紹介してきたアイデアを論文にしていく予定ですので、ご期待ください。
- Tadanori Yamaguchi, Hajime Matsui, Hisae Miyahara, Hiroshi Kubota, Naoki Hirose. Quantitative relationship of Sr:Ca of statoliths of the Japanese flying squid (Todarodes pacificus) with empirical water temperatures. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 105, e14, 1–11, 2025.