23. それ、マツイカです!
スルメイカ(Todarodes pacificus)の不漁は漁業者だけではなく、加工業者や飲食業者、そして我々消費者にも大きな影響を与えるようになりました。少し前までは値段が上がったというレベルのニュースだったのですが、現在ではイカがないというレベルになっています。ついには、イカの代替食品として、コンニャク粉からつくった蒲鉾が開発されたそうです。ひょっとしたら、カニ蒲鉾のように、いずれ別種の食品として認知されるようになるかもしれませんね。
もちろんスルメイカの不漁は日本だけでなく、韓国でも深刻で、以前ブログで紹介したように、「台湾産スルメイカ」や「中国産スルメイカ」が流通していて、実はそれらが別種のアルゼンチンマツイカ(Illex argentinus)である可能性が高いことが分かっています。日本では、食品表示法(平成27年施行)により一般的な名称と原産地の表示が義務づけられているので、スルメイカと称して流通することはないと思っていましたが、最近では紛らわしい事例がでてきているようです。
たとえば、テレビなどでも通販商品として宣伝しているイカの開き干し。函館の港で炭火焼している映像が流されて、とても美味しそうなのですが、画面の下に小さく書いてある原産地は、「アルゼンチン・カナダ・国産」でした。現在、値段から考えて国産スルメイカが入っている可能性は極めて低く、またカナダやアルゼンチンにスルメイカは生息していないはずです。かなりアヤしいですね。
実は対馬海峡や山陰沿岸で漁獲されるケンサキイカ(Uroteuthis edulis)も今ではずいぶん減っていて、ケンサキイカの干物として販売されている商品のほとんどは、原産地がタイやベトナム産になっています。もちろんタイやベトナムの沿岸にもケンサキイカは生息していますが、干物になるほど大きくは成長しません。なので、加工品として輸出されるのは同じ属の別種で、ヒラケンサキイカ(Uroteuthis chinensis)やアジアケンサキイカ(Uroteuthis duvaucelii)です。ケンサキイカと極めて近い種なので、味やテイストの差異は少なくともイカ男には分かりません。Uroteuthis属をかりにケンサキイカ属とみなせば、一般的な名称として許容の範囲かなとおもいます。
しかし、スルメイカとアルゼンチンマツイカは属が違う別種です。件の加工品の原材料表示が「マツイカ(アルゼンチン・カナダ・国産)」であればセーフですが、「スルメイカ(アルゼンチン・カナダ・国産)」であればアウトではないかなと思います。で、実際はどうかというと・・・。
3年前のCIAC(国際頭足類科学諮問委員会)で頭足類の流通に関するトレーサビリティが問題になったという話を聞いたとき、まさか日本でもここまで深刻な事態になるとは考えもしませんでした。貧すれば鈍する。米をふくめて食料品が高騰しているいまの日本で、お手頃の安い商品があったとしても、どんな素性の材料を使っているか末端の消費者には知りようがありません。ちょっと怖くなってきますね。
- Ian G. Gleadall, Hassan Moustahfd, Warwick H. H. Sauer, Lahsen Ababouch, Alexander I. Arkhipkin, Jilali Bensbai, Isa Elegbede, Abdelmalek Faraj, Pedro Ferreiro‑Velasco, Roberto González‑Gómez, Carmen González‑Vallés, Tadanori Yamaguchi, et al. Towards global traceability for sustainable cephalopod seafood. Marine Biology, 171:44, 2024.

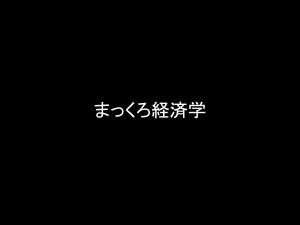

はじめてコメントさせて頂きます。
去年は、中国向け水産物輸出停止の影響もあってか、大西洋で操業していた日本隻船がアルゼンチンマツイカを函館で水揚していましたので、これを含めてマツイカ(アルゼンチン・カナダ・国産)の表記にしていると思いたいですね。
コメントありがとうございます。マツイカとして売られていれば問題はないですね。しかし韓国では、アルゼンチンマツイカを「外国産スルメイカ」として売られている場合があるようです。スルメイカが減少して大変だとは思いますが、日本の漁業者さんには信用を大切にしてほしいです。