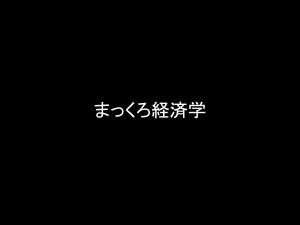13. 生物の栄枯盛衰
ハビタット解析(Habitat analysis)は、生物が生息する環境(ハビタット)に関する情報を分析し、その生物がどのような環境条件で生息しやすいか、または分布しやすいかを評価する手法です。具体的な研究例としては、環境変数(水温、塩分、深さ、地形、底質など)と生物の分布との関係を解析して、将来的な分布や生息可能域を予測し、気候変動や人間活動による環境変化が生物の生息環境にどのような影響を及ぼすかを評価します。特に水産有用種については、産卵場や成育場の適地を特定し、資源管理や漁業への応用が可能なので、現在盛んに研究されています。
いま水産業で漁獲対象物になっている生物種についてハビタット解析を用いて調べると、多くの種がふ化後、餌が豊富な海域に流されて成長し、ある時期になると適切な海域で産卵します。まるで、能動的に最適な産卵場所をさがして移動しているかのようです。本当でしょうか。
イカ男が30数年前就職した頃は、1人で公用車をつかって初めての場所に出張するのは大変でした。事前に道路地図とゼンリン地図を何枚もコピーして道順の印をつけ、行ったことがある人にどのくらい時間がかかるかを尋ねました。当日の運転中も交通標識やまわりの建物に注意しながら、横目で地図のコピーを確認しなければならず、今から思うとかなり危なっかしい運転で、事故にならなくてほんとうによかった。現在ではカーナビに情報を入力するだけで、正確に案内してくれます。慣れてしまうと、行きたい場所に都合のよい時刻に到着できることは当たり前のように思えてきますが、これは大間違いです。特に若い人はコスパや対パを重視しますので、無駄足をふんだり、迷い迷いしながら場所を探すのを嫌がるかもしれませんが、ひと昔前まではそれが当然だったのです。
このように人間でも正確な方角と距離を把握して移動するのは困難なわけですから、動物であればなおさらです。まして、目印が極端に少ない海の中をおよぐ海洋生物であれば言わずもがなでしょう。しかも海には海流があり、陸上であればひどい地震で道が上下左右に動いているような状況です。想像を絶しますね。
このようなことからイカ男は、主要な漁業対象種が適切な索餌海域と産卵海域を行き来しているようにみえるのは、偶然にそのような海域を行き来するような行動パターンを持っている種の個体数が増えて、その結果主要な漁業対象種になったからだと考えます。したがって、もし少しでも環境が変わって、独自の行動パターンとのズレが生じた場合、ドミノ倒しのように再生産サイクルが崩壊していく可能性があります。現在スルメイカでおこっている資源減少がまさにこれだとイカ男には思えるのです。
もしこの説が正しいのであれば、たとえばウミユリやオウムガイ、シーラカンスなどのように、いま細々と生息しているマイナーな生物種にも過去に大繫栄した歴史があるのかもしれません。
また、主に軟体動物の系統解析をおこなっている知人は、生物種の数と生物の数量は比例せず、むしろ逆の関係になると話しています。つまり、生物の数量が多いときは種の数が少なく、種の数が多いときは全体の数量が少ないということです。かりに、少数の種が環境に適応して爆発的に増加して生物量を増やしたあと、何らかの原因で環境が変化して生物量が減少したとしましょう。その後、いろいろな海域に取り残された集団がそれぞれその環境に適応するように進化すれば、近縁種として種の数が増えることになります。
2000年前後に大量に漁獲されていたスルメイカの漁獲量は現在1/10以下にまで減少しました。この原因について、イカ男は水温上昇が原因だと考えていますが、この程度の水温上昇は少なくとも平安期には起こったようですし、縄文期にはもっと上昇していたはずです。平安期以前や縄文期以前にスルメイカがどのていど生息していたかは知りようがありませんが、そこそこの数が生き残ってきたのではないでしょうか。少なくともウミユリやオウムガイ、シーラカンスが経験したような過激な減少だったとは思えますん。
我々はせいぜい過剰漁獲をやめて、スルメイカがどこかで生き残れるよう配慮してあげようではありませんか。